はじめに

2025年8月、金融庁は「令和8(2026)年度税制改正要望」を公表しました。今回の要望には、NISA制度のさらなる拡充や暗号資産課税の見直しなど、資産形成を推進するための重要なテーマが含まれています。主な項目をわかりやすく整理しました。
結論

NISA拡充・暗号資産課税の見直しがますます投資家にとって追い風になりそうです。まだ「要望」段階なので、実際に制度が変わるのは早くても2026年以降です。
- NISAを活用する(まずは少額のつみたてからでもOK)
- 暗号資産に興味がある人は、少額で勉強してみる(制度改正に備えて慣れておく)
- ニュースをチェックする習慣をつける(制度変更をいち早くキャッチできる)
今から準備しておくことで将来の制度変更をしっかり活かしましょう!
「資産運用立国」の推進
日本を「貯蓄から投資へ」と導くため、NISA制度や投資法人関連の税制優遇が重点要望として盛り込まれています。
◆ NISAの拡充
NISAとは、投資で得た利益に税金がかからない制度のこと。
通常は利益の20%ほどが税金で引かれてしまいますが、NISAなら丸ごと手元に残ります。年間最大360万円、生涯で最大1,800万円まで投資ができ、非課税で運用できます。
- 現状:NISAは若年層から高齢層まで幅広い世代で利用が進んでいる
- 要望:
- つみたて投資枠の対象年齢の見直し(子ども支援策として)
- 投資信託・株式に加え、より多様な商品を対象に拡大
- 非課税保有限度額を「当年中の復活」可能にして入替をしやすく

2025年5月31日に、【ついに始まる?】「こどもNISA」って本当におトクなの?【子育て世代必見】という記事を書きました。
つみたて投資枠の対象年齢の見直しは、教育費の準備や将来への資産形成がますます重要視される今、子育て世代にとって大きな味方になりそうです。
◆ 所在地確認手続きの簡素化
- NISA口座開設から10年ごとに金融機関が住所確認を行う現行制度は、投資家・金融機関双方に負担大。
- 郵送以外の方法を認めるなど、簡素化を要望。
◆ 投資法人への税制優遇の延長
- 再エネ投資を促す「インフラファンド」の税制優遇を延長・緩和。
- 匿名組合出資における制約も緩和し、共同投資を進めやすくする。
暗号資産
◆ 暗号資産取引の課税見直し
- 現状:株式は分離課税だが、暗号資産は総合課税(最高55%課税の可能性)。
- 要望:分離課税の導入を含めた見直し。将来的に「暗号資産ETF」の検討も。
現行の課税イメージ(総合課税)
| 課税所得金額(給与+暗号資産利益など) | 所得税率 | 住民税率 | 合計税率 |
|---|---|---|---|
| 〜195万円 | 5% | 10% | 15% |
| 195万円超〜330万円 | 10% | 10% | 20% |
| 330万円超〜695万円 | 20% | 10% | 30% |
| 695万円超〜900万円 | 23% | 10% | 33% |
| 900万円超〜1,800万円 | 33% | 10% | 43% |
| 1,800万円超〜4,000万円 | 40% | 10% | 50% |
| 4,000万円超 | 45% | 10% | 55% |
👉 つまり、所得が多い人ほど暗号資産投資に不利な状況です。
見直し案(分離課税)との比較
| 項目 | 現行ルール(総合課税) | 見直し案(分離課税) |
|---|---|---|
| 税率の仕組み | 給与などと合算し、累進課税(15〜55%) | 利益に一律20%前後(所得に関係なし) |
| 所得が少ない人 | 税率15〜20%程度 | 税率20%程度 |
| 所得が多い人 | 最大55%の税率 | 税率20%程度 |
| 計算の手間 | 他の収入と合算して計算する必要あり | 暗号資産の利益だけで計算できシンプル |
具体例でシミュレーション
- 年収600万円、暗号資産利益100万円
→ 現行:税率33% → 税金約33万円
→ 見直し後:税率20% → 税金20万円 - 年収2,000万円、暗号資産利益500万円
→ 現行:税率50% → 税金250万円
→ 見直し後:税率20% → 税金100万円
👉 所得が多い人ほど負担減の効果は大きいですが、中堅サラリーマン層にとってもメリットがあります。
保険
◆ 生命保険料控除の恒久化
- 2025年度は「子育て世帯向け特例」として、23歳未満の扶養親族がいる場合に所得控除を2万円上乗せ。
- 要望:この特例を一時措置ではなく恒久化。
国際金融センターの実現
◆ 外国組合員への課税特例の緩和
- 海外投資家(LP)が日本のファンドに投資する際の非課税特例を緩和・手続き簡素化。
◆ クロスボーダー投資の税務手続き見直し
- ファンドを通じた投資における「投資家単位での租税条約申請」が実務上困難。
- 手続きを簡素化し、投資促進を図る。
◆ 金融所得課税の一体化
- 現在は株式や公社債に限られる損益通算の範囲を、デリバティブ・預貯金まで拡大することを要望。
その他の要望項目
- 東日本大震災関連の印紙税非課税措置の延長
- 教育資金一括贈与の非課税措置延長
- 企業年金の特別法人税の撤廃または課税停止延長
- 海外ファンドとのレポ取引非課税の恒久化
- 相続税に関する見直し(死亡保険金の非課税枠引上げなど)
まとめ
今回の要望は、「資産運用立国」を推進するために、
- NISAのさらなる拡充
- 暗号資産課税の見直し
- 保険控除の恒久化
- 国際金融センター実現に向けた税制整備
が大きな柱となっています。
終わりに

実際にどの要望が税制改正に反映されるかは、2025年末に公表される「税制改正大綱」で明らかになります。投資家・子育て世帯にとって大きな影響を持つため、今後の動向に注目です。
まだ確定ではありませんが、資産形成のチャンスが広がる可能性は十分あります。
「いつ制度が変わってもいいように」今のうちからNISAを活用し、投資の第一歩を踏み出しておくのがおすすめです。


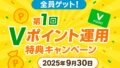
コメント